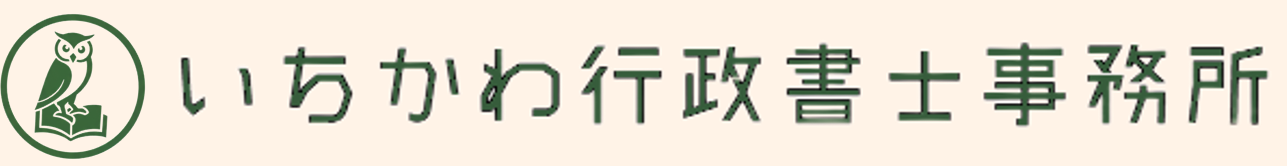インバウンド需要の回復や空き家の活用ニーズを背景に、「民泊を始めたい」と考える不動産オーナーや個人の方が増えています。
しかし、民泊は単に部屋を貸せばよいというものではなく、法律に基づいた手続きや許可申請が必要です。ここでは、民泊開業に必要な手続きと許可申請の流れをわかりやすく整理します。
民泊の開業方法は大きく3種類
まず、民泊を始める方法には大きく分けて以下の3つがあります。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)
届出制。年間180日以内の営業制限あり。 - 旅館業法に基づく簡易宿所営業
許可制。営業日数に制限はないが、施設要件が厳格。 - 特区民泊(国家戦略特区)
一部の自治体で導入。条例に従って認定を受ける。
自分の物件の立地や利用目的によって、どの方法を選ぶかを決める必要があります。
民泊新法(住宅宿泊事業)の届出手続き
最も利用されるのが「住宅宿泊事業」です。手続きの流れは以下のとおりです。
- 届出先の確認
都道府県または政令市・中核市の担当窓口(保健所など)へ届出。 - 必要書類の準備
住民票や登記事項証明書、建物の図面、管理体制を示す書類、近隣住民への事前周知の記録など。 - 消防法の適合確認
消防設備(消火器、火災報知器など)の設置が必要。消防署への相談が必須。 - 届出の提出と受理
書類が受理されれば事業者番号が付与され、営業開始が可能となります。
旅館業法に基づく民泊(簡易宿所)の許可申請
「年間を通して民泊を運営したい」「大人数で利用できる施設をつくりたい」という場合は、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得します。
流れ
- 保健所へ事前相談
- 建築基準法・消防法の確認(用途変更が必要な場合も)
- 必要書類の作成(図面、施設の概要、管理体制など)
- 保健所に申請 → 立入検査 → 許可取得
旅館業法による営業は、営業日数の制限がなく、安定した運営が可能ですが、その分、要件が厳しい点に注意が必要です。
特区民泊の認定手続き
東京都大田区や大阪市など、一部自治体では特区民泊制度が導入されています。
条例に基づき、2泊3日以上からの宿泊が可能となるなど、柔軟な運営ができるケースもあります。
ただし、自治体ごとに条件や手続きが異なるため、事前に確認が欠かせません。
民泊開業に共通して必要な準備
- 建築基準法の用途確認(住居として使えるか)
- 消防法に基づく設備の設置
- 近隣住民への周知と説明
- 衛生管理・清掃体制の確立
- 宿泊者名簿の作成義務
これらを怠ると、開業後に行政からの指導や近隣トラブルにつながります。
行政書士に相談するメリット
「民泊 開業 手続き」や「民泊 許可 申請」を調べると多くの情報が出てきますが、実際に進めるとなると非常に煩雑です。
特に、消防署や建築指導課との調整、図面の作成、自治体独自のルールへの対応は専門知識が求められます。
行政書士に依頼することで、
- 書類作成・届出の代行
- 行政窓口との折衝サポート
- 民泊や旅館業に特化したノウハウの提供
- 地域密着で自治体ごとの条例にも対応
といったメリットがあります。初めて開業する方にとっては、安心してスタートできる大きな助けとなるでしょう。
まとめ:正しい手続きを踏んで安心の民泊運営を
民泊を始めるには、住宅宿泊事業の届出・旅館業法の許可・特区民泊の認定といった複数の方法があり、それぞれ手続きや要件が異なります。
共通して重要なのは、消防・建築・近隣対応を含め、法律に基づいた準備を整えることです。
「自分でやるのは不安」「最短で開業したい」という方は、専門の行政書士に相談するのが安心です。
当事務所へのご相談はLINEからも可能です。下のボタンを押して友だち追加してください。