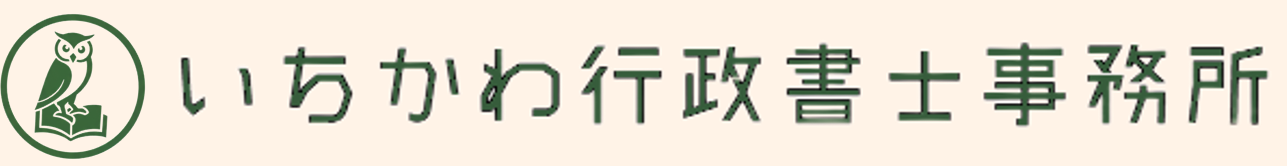近年、訪日外国人の増加や新しい宿泊スタイルの定着により、「民泊」に注目が集まっています。しかし、民泊を運営するには、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づいたルールを理解し、適切に手続きを行う必要があります。本記事では、これから民泊を始めたい方に向けて、法律の概要と実務上のポイントを解説します。
住宅宿泊事業法の目的
住宅宿泊事業法は、2018年(平成30年)に施行された比較的新しい法律です。その目的は、
- 外国人観光客をはじめとする宿泊需要に対応すること
- 健全で安心な宿泊サービスを提供すること
- 近隣住民とのトラブルを防止すること
を掲げています。これにより、民泊が法的に位置付けられ、健全な市場の形成が進められました。
民泊の営業日数制限
大きな特徴として、民泊は年間180日以内しか営業できないという制限があります。これは、旅館業との差別化を図るための規定であり、住居としての利用とのバランスを取るための仕組みです。不動産オーナーにとっては、投資回収や運営計画を考える際に重要なポイントとなります。
届出制度と必要書類
民泊を始めるには、都道府県知事(または政令市・特別区長)への届出が必要です。許可制ではなく届出制ですが、必要な書類や図面を揃える必要があり、手続きは決して軽視できません。
主な提出書類は以下のとおりです:
- 届出書(住宅ごとに作成)
- 住宅の図面(間取りや設備の位置を記載)
- 賃貸住宅の場合はオーナーの承諾書
- マンションの場合は規約で禁止されていないことの証明
提出が受理されると「届出番号」が発行され、正式に営業が可能となります。
宿泊者に関する義務
民泊運営者には、宿泊者や地域住民に対して守るべきルールがあります。
- 宿泊者名簿の作成・保存
宿泊者の氏名・住所・職業、外国人の場合は国籍とパスポート番号を記録し、3年間保存する義務があります。 - 衛生管理
居室は1人あたり3.3㎡以上を確保し、清掃・換気を定期的に行うことが義務付けられています。 - 安全確保
非常用照明や避難経路の表示を設置し、災害時に備える必要があります。 - 外国人対応
設備案内や交通手段の情報を外国語で提供することが求められます。 - 周辺住民への配慮
騒音防止やゴミ出しルールなど、地域環境に配慮した説明を宿泊者に行う必要があります。
行政による監督と罰則
民泊事業者は、都道府県知事からの指導・監督を受ける対象です。業務改善命令や業務停止命令を受けることがあり、違反が悪質な場合には事業廃止命令や罰則(罰金・刑事罰)も科される可能性があります。特に無届営業は厳しく取り締まられており、注意が必要です。
行政書士に相談するメリット
届出制とはいえ、必要書類の準備や要件確認は煩雑です。また、マンション規約や賃貸借契約の確認、管理業者との契約書面など、実務でつまずきやすいポイントも多くあります。専門知識を持つ行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 書類作成や提出をスムーズに代行してもらえる
- 条例など地域ごとの規制を調査してもらえる
- 開業後の運営管理(名簿や報告義務)もサポートしてもらえる
特に東京など都市部では条例による制限も強く、地域事情を把握した専門家に相談することで、安心して民泊をスタートできます。
まとめ
住宅宿泊事業法に基づく民泊運営は、
- 年間180日の営業制限
- 行政への届出義務
- 宿泊者・地域住民への配慮
といったルールを守ることが大前提です。これらを正しく理解していないと、せっかくの民泊ビジネスが違法運営となり、思わぬリスクを背負うことになりかねません。
これから民泊を始める方は、まず制度を正しく理解し、専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所へのご相談はLINEからも可能です。下のボタンを押して友だち追加してください。